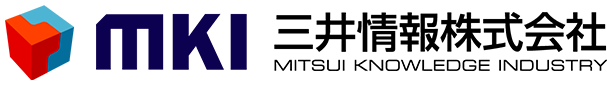Wi-Fi 6をご存知ですか - 後編 -
74ユーザの同時通信
※今回のコラムは、「Wi-Fi 6をご存知ですか」の後編です。前編はこちらからご覧ください。
前回のコラム、「Wi-Fi 6をご存知ですか -前編-」でもお話ししました通り、無線LANでは送信・受信が同時に出来ないだけでなく、そもそも同じ無線周波数(チャネル)では同時に1台のデバイス(端末・AP(アクセスポイント)含む)しか送信ができません。最近では1APに50台以上の端末が繋がることもありますが、これら大量の端末とAPが1台ずつ順番待ちをしながら送受信をしていることになります。トータルのスループットも全機器で奪い合いますし、通信の待ち時間などが遅延に影響してしまいます。
有線LANならば当たり前のようにできる同時通信が出来ない。ということが、これまでの無線LANの課題でした。特に複数の端末が小さなパケットの通信をしようとする時に、現在の方式は電波の使い方に無駄が多く、非効率な通信となっていました。そこでWi-Fi 6には、LTE通信でも使われている“OFDMA”(Orthogonal Frequency Division Multiple Access、直行周波数分割多重接続)という変調方式が追加されました。
前回のコラムでご紹介した1024QAMはデジタル信号を特定周波数の電波に載せるための変調でした。これを一次変調と呼びます。無線LANではさらにこの信号を複数の周波数に散らせるスペクトラム拡散の二次変調をかけます。この二次変調に従来の“OFDM”(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、直行周波数分割多重)ではなく、LTE通信で実績のあるOFDMAが採用されました。
■スペクトラム拡散
ノイズから守るため、周波数を散らす(拡散)。その代わり出力を落として他の機器への影響を減らす。
新しく採用された変調方式OFDMAでは周波数を分割することで複数端末の同時通信を実現します。従来のOFDMではどんなに小さなデータを送る際にも周波数は最小20MHz幅(チャネル1個分)で送信をしていました。OFDMAでは約2MHzを最小単位(RU:Resource Unit)として9ユーザが異なる周波数で同時通信できることになります。今までは時間単位で1ユーザが周波数を占有していましたが分割利用することで効率を向上する仕組みです。Wi-Fi 6の最大周波数幅160MHz(チャネル8個分)のときには、74ユーザが同時通信できるということになります(送信・受信は同時には出来ません)。これは、この後に紹介する「高密度環境」においても小さいパケットを効率よく同時通信することで大きな通信改善が見込めます。
Wi-Fi 6のOFDMAはダウンストリーム・アップストリームの両方をサポートします。特にアップストリームでは端末の送信タイミングをAPでスケジュール制御することが出来るようになるので、AR/VRといった低遅延要件の通信やQoS(Quality of Service)のような品質の優先付けなどにも期待できます。
OFDMAでは周波数を細かく分割することで同時通信を実現しますが、Wi-Fi 6ではもう1つストリーム(≒アンテナ)を分割して同時通信を行うMU-MIMO(マルチユーザMIMO)という技術があります。この技術では8ユーザが同時通信できますし、一定条件下ではOFDMAとの組み合わせも可能です。こちらの詳細は後述の雑誌寄稿で触れています。
高密度環境の干渉を軽減する
無線LANでは同じチャネルで通信出来るのは1台のみという原則があります。スタジアム等の競技場やイベント会場、学校や駅といった人が密集する場所では多くのAPを配置する必要があります。そうすると、近隣のAP・端末と同じチャネルを使用するといったケースが出てきます。チャネルが同じであれば例え他のAPに繋がっている端末同士であっても通信権を奪い合うことになります。端末やAPは自分が通信を始める前に電波をチェックし、一定強度の通信を検知すると自分は送信せずに待機してしまいます。
Wi-Fi 6では、この状況を打破すべくBSS(Basic Service Set)COLORINGという機能を実装しました。BSS COLORINGではAPとそこに接続する端末をグルーピングして「色」を付与します。通信前の電波チェックで同じ色の通信を検知した場合は、従来どおり厳重なしきい値で評価して、強い電波強度であれば自身の送信は止めて待機します。しかし、もし異なる色の通信を検知した場合はチャネルが同じであっても別の場所で別システムが通信しているものとして、しきい値を動的に変更します。同じ色の通信を検知した場合に比べて「他端末が通信中」と判断する基準を緩和しているので、自分が送信できるチャンスが増大することになります。
実は、MKIが提供するスタジアムWi-Fiと呼ばれる高密度Wi-Fi環境ではWi-Fi 6登場以前からAPメーカの独自機能により類似した干渉軽減方法を採用していました。これはAP側だけの機能でしたが、Wi-Fi 6では標準化されて端末側も対応することになります。結果、高密度な環境であっても各端末の送信機会が改善し、少ない無線資源を無駄なく効率的に利用することができるようになります。
ついにIoT端末にも恩恵が
Wi-Fiに対応したIoT端末も多く登場していますが、実はWi-Fi 5までの規格はIoT端末に優しくない設計でした。IoTの世界では一般のオフィスPCなどと違いトラフィックに特徴があります。それは、少ないデータを低頻度で長距離に飛ばしたいというものです。温度センサーなどでは、30分に一回、ちょっとした文字列を送るだけと言ったものも多く存在します。普段はスリープしていてたまに起きるといった動作から、小型電池やエナジーハーベスティング(環境発電:太陽光や熱や振動で発電)を使った低消費電力駆動が望まれています。
Wi-Fi 6ではこれらIoT端末に対して、通信の長距離化(ノイズ耐性強化)と省電力化(スリープ強化)がはかられました。特にTWT(Target Wake Time)という省電力機能によりIoT端末に優しい通信が実現します。
今までも省電力機能は存在していました。端末が通信をしていないときには、一定間隔(100ms)で送信されるビーコンフレーム×n回分(DTIM)のタイミングで一斉に起こされるというものです。DTIMが5回分(500ms)に設定されていれば、その間は、端末はスリープすることができました。ところが、しばらく送受信予定もないのにすべての端末が定期的に一斉に起こされるということには変わりありません。IoT端末では極端な例だと1日1回しか通信しないものもあり、本来であればその間はディープスリープできることが望ましいです。
TWT機能では、APと端末間で個別に起動タイミングを事前にスケジューリングすることができます。端末は次の起動タイミングまで長期のディープスリープに入ることができ、他の端末を起こすタイミングにも影響されなくなります。個々の端末にスリープが最適化されることで容量の大きいバッテリーが搭載できないようなセンサー類でも低コストで設置できるWi-Fi環境が検討できるようになるでしょう。
MKIはWi-Fi 6の実験を重ねています
前回のコラムからここまで説明してきました通り、Wi-Fi 6は様々な機能拡張によってユーザにより良い通信環境を提供することになるでしょう。一方、機能が複雑化したことによって、導入時のテストや効果検証もより複雑化したということが言えます。
そこで今回、MKIではシスコシステムズ社のWi-Fi 6 APをいち早く入手し、Wi-Fi 6の効果や導入時の検討事項を明らかにするための試験を実施しました。
検証結果は日経NETWORK1月号(2019年12月28日発売)の特集記事の中で紹介されていますので、是非ご覧いただければと思います。
なお、今回の試験ですべての機能を確認できたわけではありません。まだ実装されてない機能や効果測定の方法を模索している最中のものもあります。MKIでは今後もさらなる検証を続け、また続報をどこかで発信させていただきます。
※日経NETWORKウェブサイト:https://tech.nikkeibp.co.jp/media/NNW/
執筆者
厚田 大輔
コア技術グループ ソリューション技術本部 次世代基盤技術部 第一技術室
2012年から無線LAN業務に従事。現場での経験を基に「ITpro Wi-Fiのウソとホントを実証」「日経ネットワーク 試してわかった! 無線LANの素朴な疑問」などでWi-Fi検証記事を連載。
木村 浩基
コア技術グループ ソリューション技術本部 次世代基盤技術部 第一技術室
2007年以来、シスコ製品の製品担当業務に従事。2012年から無線LAN製品をメインにサポートしています。
コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。
また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。