偶然の出会いが、未来を動かすことがあります。
私にとって「Sansan Innovation Tour in 徳島」への参加は、まさにそんな体験でした。
きっかけは、ふと届いた一通の招待状でした。
ちょうど、世界的なネットワーク企業Ciscoが主催するイノベーションコンテストにエントリーし、挑戦テーマを模索していた矢先、5月に開催された新規事業大会議へ参加し執筆したコラム*をきっかけに、Sansan株式会社から本ツアーへのお誘いが舞い込んできたのです。
*コラムはこちらよりご覧ください。
“正解のない時代”に挑む──三井情報が踏み出す、イノベーションの第一歩
コンテストへの挑戦と、徳島の阿波踊り。
一見無関係に思える二つの出来事が重なり合ったとき、新しい発想──たとえば「Cisco×感情(踊り)」という新結合──が生まれはじめました。
徳島の地での学びは、「成り行きの未来」、「小さな出会いが未来につながる」といった言葉に象徴されるように、地域づくりとイノベーションの本質に迫るものでした。そこで私は、自分の中で漂っていた着想に輪郭を見出すことになったのです。
本稿では、この徳島での体験を手がかりに、「偶発が未来をひらく」というテーマを振り返りながら、三井情報としてのこれからを考えていきます。
イベント概要
- 主催:Sansan株式会社
- 日程:2025年8月14日(木)~15日(金)
- 会場:徳島(Sansan藍場浜演舞場、神山まるごと高等専門学校)

DAY1:阿波踊りとイノベーション
踊る共同体が生むイノベーション
初日のプログラムでは、阿波踊りの歴史や文化的背景を学びました。その中で阿波踊りは単なる娯楽や観光資源ではなく、人々をつなぐ「社会的インフラ」として機能してきたことが強調されていました。
「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」という言葉は、観客として聞いているだけでは分からない“熱”の正体でした。
イノベーションもまた、観客席から眺めているだけでは生まれません。自ら輪に入り、踊り出す側に回ることで初めて動き出す。三井情報としても、受託の枠にとどまらず、自ら踊り出す存在である必要があるのだと感じました。

徳島初上陸!とウェルカムソーメン

その場の偶発的な出会い!
踊って気づく“共創のエネルギー”
実際に輪に入り、自ら踊り出してみると、技術的な上手下手を超えて、踊りの連と観客の一体感がすぐに生まれることを体感しました。最初は照れやぎこちなさがありましたが、リズムに身を委ねるうちに自然と笑顔が広がり、周囲との境界が溶けていく。そこには、言葉を介さずとも人を巻き込み、場を立ち上げていく力が確かにありました。
踊りやリズムといった非言語の要素は、論理や計画では生み出せない“場のエネルギー”を引き出します。これはまさに、イノベーションの現場でも必要とされる要素だと実感しました。頭で理解するだけでなく、体を通じて共感が連鎖し、共創が加速していく――阿波踊りの実践は、その本質を体で学ぶ機会となりました。


夕暮れから夜へ──時間と熱狂がつなぐ、偶発の共創、阿波踊り
DAY2:神山町から学ぶ地域づくりとイノベーション
「成り行きの未来」への抵抗
二日目は舞台を神山町に移し、地域づくりやイノベーションに取り組む実践者からの講義を受けました。神山町は人口減少や高齢化といった課題を抱えつつも、移住促進やアートプロジェクト、サテライトオフィスの誘致など、多彩な活動で注目されてきた地域です。
そこで印象に残ったのは「成り行きの未来」という言葉でした。未来は大きな戦略だけで決まるのではなく、日々の小さな選択や偶然の積み重ねによって形づくられるという視点です。しかし、もし今のままの“成り行き”に任せ続ければ、神山町では人口減少や高齢化がさらに加速し、持続可能性が失われていく可能性があります。
この話を自分たちに引き寄せれば、三井情報にとっての「成り行きの未来」とは何でしょうか。現状の延長に甘んじれば、労働集約型モデルの限界や人材不足の深刻化によって、停滞が加速しかねない現実が浮かびます。小さな出来事を積み重ね、そこから学びや新しい関係性を紡ぎ取ることができれば、「成り行きの未来」に流されるのではなく、未来を意志あるものとして描き直せるはずです。
だからこそ私たちも、日々の挑戦や小さな選択を積み重ね、未来を能動的に描き直す必要があるのだと強く感じました。


神山まるごと高専。大自然に囲まれて
「風の人」と「土の人」がつなぐイノベーション
講義の中で紹介された「風の人と土の人」という比喩も示唆的でした。外から新しい風を吹き込む人(風の人)と、地域に根を張り支える人(土の人)。
これはイノベーションのあり方にも重なります。外部の視点や技術を取り込むだけでも不十分であり、また内部の努力だけでも限界があります。両者の関係性をデザインし、交わりを意識的につくることこそが変革の持続につながるのです。
他社の事例でも、トップダウンの戦略だけでなく、社員一人ひとりの小さな挑戦や地域との関わりが成果に結びついていました。「一人の移住者」、「一度のイベント」といった小さなきっかけが未来を変える可能性を秘めています。この気づきは、神山町の実践とも深く共鳴していました。

高専の地産地食給食!

ひとつの実に、いくつもの種──多様な可能性(🌰)が眠る
学びの整理──偶発と持続可能性
阿波踊りにせよ神山町の取り組みにせよ、共通しているのは「偶発とつながりを受け入れる姿勢」でした。効率や合理性を重んじる仕事の世界では、予測不能な要素はリスクとして排除されがちです。しかし、地域や文化の現場では、むしろその偶発とつながりこそが変化や創造の源泉になっています。
阿波踊りの一体感も、神山町の「成り行きの未来」も、小さなきっかけや出会いの積み重ねから生まれるものです。私たちがイノベーションに取り組む際にも、完璧な計画を求めるのではなく、思いがけない出来事を許容し、取り込んでいく柔らかさが必要だと学びました。

学びのアーチから広がる未来

未来を育む学びの道
自分ごとへの接続──「Cisco×感情(踊り)」
こうした学びを経て、私は自分が挑戦しているCiscoのイノベーションコンテストを捉え直しました。
阿波踊りが非言語で人を巻き込み、場をつくるように、テクノロジーもまた人の感情を可視化し、つながりを深める力を持ちうるのではないか。そう考えたとき、「Cisco×感情(踊り)」という発想が、突飛な思いつきではなく、必然性を帯びた挑戦として立ち上がってきたのです。
思いがけない出会いや体験を重ねることで、散らばっていた知識や経験がつながり、新しい方向性を描き出す。これこそ「新結合」であり、三井情報としても受託型の延長線ではなく、偶発を活かした挑戦を続け、自らの未来を切り拓くために必要な道だと確信しました。
おわりに──未来への問いかけ。
徳島という場には、阿波踊りをはじめとする文化と、神山町のような挑戦が共存し、外からの風と内からの土が交わりながら未来を形づくってきました。今回のツアーでの学びと出会いは、その縮図のようでした。
偶然の出会いを点で終わらせず、どう育て、つなげていくかが、これからの私たちの問いです。
実際、2025年5月よりコラムの執筆を開始して、思いがけない出会いや共創の芽が生まれはじめています。まだ小さな種にすぎませんが、社外の異なるプレーヤーとつながることで芽吹きはじめています。
その芽がやがて森となり、未来を形づくる力になるのだと信じています。
思いがけない出会いを大切にし、それを共有し、つなげていくこと。その文化を根づかせることが、未来をひらく力になる。徳島での体験を通じて、その確信を新たにしました。


変わるのは空と光、変わらないのはこの景色
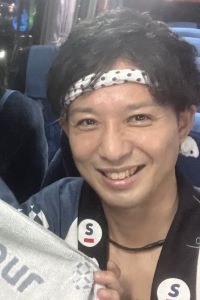
前川
イノベーション推進部 第二技術室
官公庁向けの IT コンサルタントとして従事後、2024 年度新設のイノベーション推進部へ異動。
現在は、自社技術を活かした共創・実証により、新規事業や社会課題解決型の価値創出を推進中。
三井情報グループは、三井情報グループと社会が共に持続的に成⻑するために、優先的に取り組む重要課題をマテリアリティとして特定します。本取組は、4つのマテリアリティの中でも特に「情報社会の『その先』をつくる」「ナレッジで豊かな明日(us&earth)をつくる」の実現に資する活動です。
コラム本文内に記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
本文および図表中では商標マークは明記していない場合があります。
当社の公式な発表・見解の発信は、当社ウェブサイト、プレスリリースなどで行っており、当社又は当社社員が本コラムで発信する情報は必ずしも当社の公式発表及び見解を表すものではありません。
また、本コラムのすべての内容は作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。












